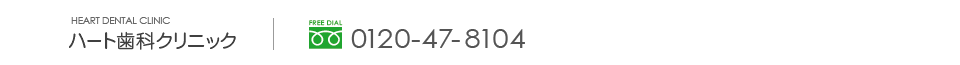穴の空いたむし歯は元には戻りません
むし歯は、ごく初期の場合治ることもありますが、一般的にはほかの病気と異なり、人間の身体がもっている自然に治す力で治ることはありません。ですから、まずむし歯にならないように予防することが何よりも大切です。
むし歯をはじめとする歯と口腔の病気は、全身のさまざまな健康状態と密接に関連することがわかっています。健康な毎日をすごすためには、まず歯と口の中の状態を良好に保つことが、大切な条件になります。
むし歯をはじめとする歯と口腔の病気は、全身のさまざまな健康状態と密接に関連することがわかっています。健康な毎日をすごすためには、まず歯と口の中の状態を良好に保つことが、大切な条件になります。
むし歯の進行
毎日歯みがきをしていても、初期のむし歯は自分では気づきにくいものです。むし歯には、進行の度合いを示す「C1」から「C4」までの大きく4つの段階があります。段階別に違いを見てみましょう。





むし歯は、三つの要因が重なった状態のまま時間が経つと次第に進行していきます。むし歯予防には、右図の内容を意識的にコントロールすることが大切です。

C1のむし歯〈エナメル質が溶け始める〉
歯の表面のエナメル質が溶け始めた段階で、比較的症状の軽いむし歯です。痛みはほとんどありませんが、たまにはしみることもあります。この段階なら、むし歯の部分を削って修復材を詰める程度の治療で済みます。

C2のむし歯〈象牙質が侵される〉
エナメル質の下にある象牙質が侵された状態です。象牙質はエナメル質ほど堅くないので、進行が早いのが特徴です。むし歯に侵された部分が深い程、冷たいものなどがしみやすくなります。

C3のむし歯〈歯髄神経が侵される〉
象牙質の下にある歯髄にまでむし歯が達した状態です。ここまでくると、歯に大きな穴があくだけでなく、歯髄炎を起こしてズキズキと激しい痛みを感じます。

C4のむし歯〈歯冠部がほとんどなくなる〉
歯冠部がほとんど失われ、根だけが残っている状態です。歯髄が死んでいれば痛みは感じなくなりますが、根が炎症を起こしたりしていると、うみが出たり悪臭があることもあります。根の炎症がひどければ、抜歯しなければなりません。
むし歯予防のポイント

三つの要素でむし歯ができる
むし歯は、三つの要因が重なった状態のまま時間が経つと次第に進行していきます。むし歯予防には、右図の内容を意識的にコントロールすることが大切です。
むし歯予防のポイント1[糖分の摂取回数を控えめにする・シュガーコントロール]
糖分を上手にコントロールすることで、むし歯菌 の養分になるものを少なくし、菌の繁殖をおさえることができます。代表的な糖分には、食べ物や飲み物に含まれる砂糖(ショ糖)や、果物に含まれる砂糖(ショ糖)や、果糖やブドウ糖などがあります。糖分の含まれる食べ物や飲み物をとる回数が少なければ、よりむし歯になりにくくなります。
むし歯予防のポイント2[ブラッシングでむし歯菌を減らす・プラークコントロール]
むし歯菌を減らすには、ブラッシングが最も一般的な方法です。正しいブラッシングによって、むし歯菌のすみかになるプラークを取り除きます。食べ物のカスがついたまま24時間経つと、歯の表面では、むし歯菌が増殖します。とくに寝ている間は、だ液の流れが弱いので、歯のエナメル質から溶け出したカルシウムやリン酸が補われず、危険な状態が長く続くことになります。そこで歯みがきをするよいタイミングは、「寝る前は必ず」「食後はできるだけ」これを毎日の習慣にすることが大切です。
むし歯予防のポイント3[フッ素の応用で歯質強化]
フッ素を歯に作用させると、歯の表面から取り込まれ、歯の結晶(アバタイト)の一部になります。フッ素を含んだ歯の結晶は、普通の歯の結晶よりも丈夫になり、むし歯菌の出す酸に対してより強くなります。ですからフッ素を適切に使うと、歯の表面が強くなり、むし歯になるのを防ぎます。また、歯のエナメル質のまわりにフッ素があると一度脱灰した部分の再石灰化を促進し、エナメル質の補修がしやすくなります。